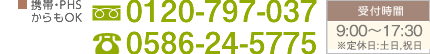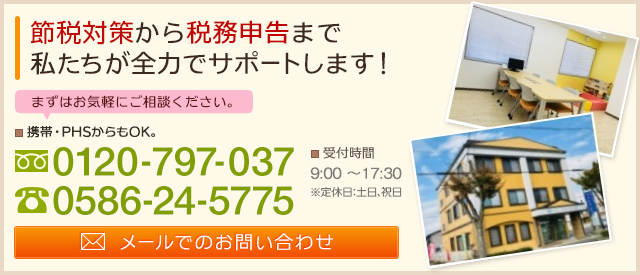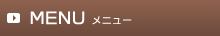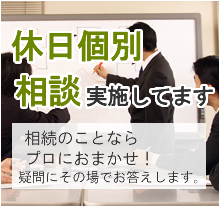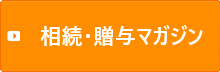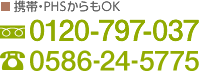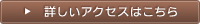相続
2023年10月18日 水曜日
養子縁組での相続対策
「養子をすると相続対策になります。」と聞いたことはありますか?
これ相続「税」対策にはなる場合もありますが、いわゆる「争族」対策としては逆効果となる場合もあり注意が必要です。
相続の計算は基礎控除(1人600万円)と累進課税の仕組み上、子供が多ければ多いほど、相続税は少なくなります。
養子縁組をすれば、「子」が増えたこととなり相続税も少なくなるという仕組みですが
相続税の計算上、その「子」としてのカウント増加になるのは1人(又は2人)までと制限があります。
ただし制限があるといっても増えることは増えるのでいくらかの相続税軽減につながります。
税金が減少してよかったねともなりません。
「争族」対策には逆効果となる可能性も秘めています。
自分の実子の配偶者(婿さん、嫁さん)を養子にした場合→婚姻関係の二人であるため何があるかわかりません。
いざ相続が起こった際に相続分や遺留分の請求があったりでもめて、婚姻関係が解消してしまうパターン
孫を養子とする場合→その孫が私も相続人だからと多くを要求する可能性は少ないですが
別の孫がいる場合に、こちらには何もないのか等の揉める要因になる可能性があります。
名字(姓)問題も考えられますが、同じ名字の場合や、婚姻で名字が変わった後の人は変わりません。
どういう事かというと
資産家の山田さん、その長男の娘がこの度結婚し、夫の姓である鈴木となった場合
その孫は祖父母(山田)の養子となっても、この場合婚姻で改姓した(鈴木)の方が強い為
養子縁組しても(山田)には戻らず(鈴木)のままです。
ややこしいですね・・・
養子縁組で相続税の対策は可能ですが
いろいろと注意する点があります。
いくら減少するのか、家族の関係性等いろいろ考慮して進める必要が有るのかなと思います。
いろいろと難しい問題もあり
勘違いして進めて後悔しないためにも一度専門家へ相談してから進めてください。
これ相続「税」対策にはなる場合もありますが、いわゆる「争族」対策としては逆効果となる場合もあり注意が必要です。
相続の計算は基礎控除(1人600万円)と累進課税の仕組み上、子供が多ければ多いほど、相続税は少なくなります。
養子縁組をすれば、「子」が増えたこととなり相続税も少なくなるという仕組みですが
相続税の計算上、その「子」としてのカウント増加になるのは1人(又は2人)までと制限があります。
ただし制限があるといっても増えることは増えるのでいくらかの相続税軽減につながります。
税金が減少してよかったねともなりません。
「争族」対策には逆効果となる可能性も秘めています。
自分の実子の配偶者(婿さん、嫁さん)を養子にした場合→婚姻関係の二人であるため何があるかわかりません。
いざ相続が起こった際に相続分や遺留分の請求があったりでもめて、婚姻関係が解消してしまうパターン
孫を養子とする場合→その孫が私も相続人だからと多くを要求する可能性は少ないですが
別の孫がいる場合に、こちらには何もないのか等の揉める要因になる可能性があります。
名字(姓)問題も考えられますが、同じ名字の場合や、婚姻で名字が変わった後の人は変わりません。
どういう事かというと
資産家の山田さん、その長男の娘がこの度結婚し、夫の姓である鈴木となった場合
その孫は祖父母(山田)の養子となっても、この場合婚姻で改姓した(鈴木)の方が強い為
養子縁組しても(山田)には戻らず(鈴木)のままです。
ややこしいですね・・・
養子縁組で相続税の対策は可能ですが
いろいろと注意する点があります。
いくら減少するのか、家族の関係性等いろいろ考慮して進める必要が有るのかなと思います。
いろいろと難しい問題もあり
勘違いして進めて後悔しないためにも一度専門家へ相談してから進めてください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2023年9月27日 水曜日
ふるさと納税
ふるさと納税は基本的に住民税(所得税)での検討をしている事が多いと思いますが
相続により財産を取得した人は、相続税も軽減される可能性があり
給与などの所得がある人が相続により財産を取得する場合、いつもより有効である可能性があります。
ふるさと納税って、あまりよく分からないからやってない。
やっているけど、よくわかっていない人の為にざっくりとした説明をします。
3万円をふるさと納税(ふるさとチョイス、さとふる、市町村に直接等)をしたとして
その市町村の特産品等が1万円分(3割程度が限度)のものが送られてきます。
3万円で1万円の商品購入だと損ですが、
申告等により、翌年の住民税等が28,000円(寄付額-2千円)少なくなるため
実質負担2,000円で1万円の何かが貰える。という仕組みです。
(お肉などはハズレが多いので最近はトイレットペーパー等生活必需品や
旅行計画前にその地域の旅行券的なものがあれば、そこに使うようにしています。)
ふるさと納税の仕組みは↑の様なもので
ふるさと納税とは言いますが、結局は所得税住民税の「寄付控除」という制度です。
これは相続税にも「寄付控除」がありますが
住民税等とは取り扱いが少し違い、
相続した財産を寄付した場合、寄付した財産がもともとなかったかのように税金を計算する制度のため
3万円寄付して、28,000円税額が少なくなるのではなく
3万円寄付してMaxでも16,500円、状況によっては数百円の税効果という可能性もあります。
ほとんどの場合、寄付額>税金効果 となりこれだけではお勧めできません。
(寄付とは言え、損得で考えた場合の話です。)
ただし給与所得や個人事業をしている人などが給与等のお金から寄付するのではなく
相続したお金から寄付した場合には
住民税等の「寄付控除」と相続税の「寄付控除」を同時に適用することも可能です。
例えば、サラリーマンが相続したお金3万円をふるさと納税で寄付した場合
相続税が3,000円安くなり、所得税が28,000円安くなる。
(税金だけで合計31,000円安く、寄付しない場合より1千円得をする)
さらに1万円程度の特産品等が貰える。という状況もあり得ます。
相続税は、相続した財産(お金)から寄付すればOKで
住民税等は、とくに取り決めが無く
あっちで使えば、こっちでは使えない。的なルールも無いからOKという理屈で
変な状況とは思いますが、Wで使う人が少なく、金額も大事にするほどでもないのかなと思うので
恐らく今後も制限するような制度はできないのかなと、個人的には思います。
※上記の説明や例等は、おおまかにわかりやすく説明しているだけであるため
詳しい規定等は専門家へご確認ください。
相続により財産を取得した人は、相続税も軽減される可能性があり
給与などの所得がある人が相続により財産を取得する場合、いつもより有効である可能性があります。
ふるさと納税って、あまりよく分からないからやってない。
やっているけど、よくわかっていない人の為にざっくりとした説明をします。
3万円をふるさと納税(ふるさとチョイス、さとふる、市町村に直接等)をしたとして
その市町村の特産品等が1万円分(3割程度が限度)のものが送られてきます。
3万円で1万円の商品購入だと損ですが、
申告等により、翌年の住民税等が28,000円(寄付額-2千円)少なくなるため
実質負担2,000円で1万円の何かが貰える。という仕組みです。
(お肉などはハズレが多いので最近はトイレットペーパー等生活必需品や
旅行計画前にその地域の旅行券的なものがあれば、そこに使うようにしています。)
ふるさと納税の仕組みは↑の様なもので
ふるさと納税とは言いますが、結局は所得税住民税の「寄付控除」という制度です。
これは相続税にも「寄付控除」がありますが
住民税等とは取り扱いが少し違い、
相続した財産を寄付した場合、寄付した財産がもともとなかったかのように税金を計算する制度のため
3万円寄付して、28,000円税額が少なくなるのではなく
3万円寄付してMaxでも16,500円、状況によっては数百円の税効果という可能性もあります。
ほとんどの場合、寄付額>税金効果 となりこれだけではお勧めできません。
(寄付とは言え、損得で考えた場合の話です。)
ただし給与所得や個人事業をしている人などが給与等のお金から寄付するのではなく
相続したお金から寄付した場合には
住民税等の「寄付控除」と相続税の「寄付控除」を同時に適用することも可能です。
例えば、サラリーマンが相続したお金3万円をふるさと納税で寄付した場合
相続税が3,000円安くなり、所得税が28,000円安くなる。
(税金だけで合計31,000円安く、寄付しない場合より1千円得をする)
さらに1万円程度の特産品等が貰える。という状況もあり得ます。
相続税は、相続した財産(お金)から寄付すればOKで
住民税等は、とくに取り決めが無く
あっちで使えば、こっちでは使えない。的なルールも無いからOKという理屈で
変な状況とは思いますが、Wで使う人が少なく、金額も大事にするほどでもないのかなと思うので
恐らく今後も制限するような制度はできないのかなと、個人的には思います。
※上記の説明や例等は、おおまかにわかりやすく説明しているだけであるため
詳しい規定等は専門家へご確認ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年6月27日 月曜日
税務調査(相続税)
相続税の申告や対策で相談中よくお客様から
「お金でもっておけばバレないよね?」
「通帳は何年前まで見れるの?」なんて聞かれる事があります。
基本的にバレます。通帳は10年分の履歴を取得できるようです。
相手(税務署)はウソを見抜くプロです。
何気ない会話の様で財産の動き等確認し、ウソや矛盾が無いか?隠している事やモノは無いかを考えてます。
例えば
税務署「被相続人〇〇さんの職歴を教えてください。」
相続人「□□会社の東京本社勤務で35歳で一宮支店へ転勤し定年退職です。」
一般的な話の様に思いますが、
・東京にある支店の銀行が無いけど申告漏れてないか?
□□会社の付き合いのある銀行は▲▲銀行だから確認してみよう。
・□□は高給だし35歳で転勤だとマンション購入等してるかも?東京の不動産等もっていないか?等々
税務署は日常会話の様な会話から、常に何か財産隠してないか?漏れていないか?を考えてます。
全部現金で受け取り支払いしていれば分からないでしょ?とも言われますが
その受け取り、支払いの相手方が通帳から出金、受取後は通帳へ入金していたり
生活費でお金使ってましたという話だったとしても
毎月の使用状況を日常会話っぽい財産確認の話とズレが生じバレます。
当然1円単位までとは行きませんが、概ねつかんできます。
亡くなられた方のお金でどこに何の支払いに使ったのか全く分からない。
なんてことも多々ありますが、一度税理士に相談してみるのがよいと思います。
ちなみに最近、暗礁乗上感のあるマイナンバーカードですが
しっかりと普及することで、パソコン一発でお金の動きが確認できるようになるかも・・・
そうなると1円のずれも無い指摘をされることになるかもしれませんね。
「お金でもっておけばバレないよね?」
「通帳は何年前まで見れるの?」なんて聞かれる事があります。
基本的にバレます。通帳は10年分の履歴を取得できるようです。
相手(税務署)はウソを見抜くプロです。
何気ない会話の様で財産の動き等確認し、ウソや矛盾が無いか?隠している事やモノは無いかを考えてます。
例えば
税務署「被相続人〇〇さんの職歴を教えてください。」
相続人「□□会社の東京本社勤務で35歳で一宮支店へ転勤し定年退職です。」
一般的な話の様に思いますが、
・東京にある支店の銀行が無いけど申告漏れてないか?
□□会社の付き合いのある銀行は▲▲銀行だから確認してみよう。
・□□は高給だし35歳で転勤だとマンション購入等してるかも?東京の不動産等もっていないか?等々
税務署は日常会話の様な会話から、常に何か財産隠してないか?漏れていないか?を考えてます。
全部現金で受け取り支払いしていれば分からないでしょ?とも言われますが
その受け取り、支払いの相手方が通帳から出金、受取後は通帳へ入金していたり
生活費でお金使ってましたという話だったとしても
毎月の使用状況を日常会話っぽい財産確認の話とズレが生じバレます。
当然1円単位までとは行きませんが、概ねつかんできます。
亡くなられた方のお金でどこに何の支払いに使ったのか全く分からない。
なんてことも多々ありますが、一度税理士に相談してみるのがよいと思います。
ちなみに最近、暗礁乗上感のあるマイナンバーカードですが
しっかりと普及することで、パソコン一発でお金の動きが確認できるようになるかも・・・
そうなると1円のずれも無い指摘をされることになるかもしれませんね。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年6月23日 木曜日
負担付贈与
アパート等の収益物件を相続税対策の為と子供等へ贈与する事があります。
アパート等を贈与できるとアパートの賃料は、その贈与を受けた者の所得となり
その家賃分、毎月贈与しているのと同じような効果がある!と思いますが
考えないといけない事が、まだまだあります。
その一つとして負担付贈与といって、アパート贈与するにあたり、
そのアパートに関する借入も一緒に贈与(アパート収入から返済してねと債務者を変更)する場合
その不動産の贈与税評価額が跳ね上がる可能性があります。
通常は相続税評価額で評価し贈与税の計算をすればよいので
相続税評価額3,200万円で
借入が3,000万円残っている場合
3,200万円-3,000万円=200万円
200万円-110万円=90万円に対し贈与税課税?とおもいがちですが
債務と一緒に贈与する場合、資産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価格を使う必要があります。
通常の取引価格の算定はまた別途説明しますが
ざっくりの説明では相続税評価額は通常の取引価格の80%程度です。
つまり相続税評価額の3,200万円÷80%=4,000万円ほどの評価となり
4,000万円-3,000万円=1,000万円
1,000万円-110万円=890万円に対して贈与税課税となり
想定していたよりも贈与税が高くなってしまった!という事があります。
負担付贈与にはお気を付けください。
アパート等を贈与できるとアパートの賃料は、その贈与を受けた者の所得となり
その家賃分、毎月贈与しているのと同じような効果がある!と思いますが
考えないといけない事が、まだまだあります。
その一つとして負担付贈与といって、アパート贈与するにあたり、
そのアパートに関する借入も一緒に贈与(アパート収入から返済してねと債務者を変更)する場合
その不動産の贈与税評価額が跳ね上がる可能性があります。
通常は相続税評価額で評価し贈与税の計算をすればよいので
相続税評価額3,200万円で
借入が3,000万円残っている場合
3,200万円-3,000万円=200万円
200万円-110万円=90万円に対し贈与税課税?とおもいがちですが
債務と一緒に贈与する場合、資産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価格を使う必要があります。
通常の取引価格の算定はまた別途説明しますが
ざっくりの説明では相続税評価額は通常の取引価格の80%程度です。
つまり相続税評価額の3,200万円÷80%=4,000万円ほどの評価となり
4,000万円-3,000万円=1,000万円
1,000万円-110万円=890万円に対して贈与税課税となり
想定していたよりも贈与税が高くなってしまった!という事があります。
負担付贈与にはお気を付けください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年6月13日 月曜日
それは課税の対象です。
相続申告の際、通帳の入手金の内容を確認していると
私「これは何の出金かご存じですか?」
お客様「これは私の車の代金支払ってもらいました。」
私「贈与税の対象となりそうですね。」
お客様「えー!車買ってもらうなんて普通じゃないの?なんで税金かかるの?」
この様な流れの会話が何度かあります。
専業主婦で夫が車を買ってもらう。(妻名義の車を買う)って特に悪いことではなく
私も同じ考えで普通の夫婦関係と思います。
(共働きだとそれぞれで購入の方が主流かなとは思いますが)
ただ、贈与税がかかる可能性があるというだけなのですが
「課税の対象です。」的な事を言うと「悪いことですよ。」と聞こえるようです。
説明の仕方など考える必要もあるのかなと思いますが
そもそも贈与税の申告漏れなんて無数にある気がします。
相続税申告のタイミングなので税理士事務所か、
税理士事務所が見過ごしても、のちのちに税務署が指摘をするだけで・・・
免許取り立てで「じいちゃんに車買ってもらったわー」ってよく聞く話ですが
110万円超えているからと税務署の調査を受けた話って聞いたことないです。
税務署(国税?財務省?)の周知不足なのか?
そもそも車購入時に他人からの支払いを受け付けるのがいけない?
住宅ローンと不動産の名義異なると指摘されるはずだから同じようにする?
銀行口座とマイナンバーで紐づけ出来たら解決できる問題なのか?
なんだかよく分からなくなってきましたが
課税の対象で申告納税漏れが悪いのではなく、期限後でも申告納税をすればOK
そして税務署の周知不足が悪いだけだと思います。
私「これは何の出金かご存じですか?」
お客様「これは私の車の代金支払ってもらいました。」
私「贈与税の対象となりそうですね。」
お客様「えー!車買ってもらうなんて普通じゃないの?なんで税金かかるの?」
この様な流れの会話が何度かあります。
専業主婦で夫が車を買ってもらう。(妻名義の車を買う)って特に悪いことではなく
私も同じ考えで普通の夫婦関係と思います。
(共働きだとそれぞれで購入の方が主流かなとは思いますが)
ただ、贈与税がかかる可能性があるというだけなのですが
「課税の対象です。」的な事を言うと「悪いことですよ。」と聞こえるようです。
説明の仕方など考える必要もあるのかなと思いますが
そもそも贈与税の申告漏れなんて無数にある気がします。
相続税申告のタイミングなので税理士事務所か、
税理士事務所が見過ごしても、のちのちに税務署が指摘をするだけで・・・
免許取り立てで「じいちゃんに車買ってもらったわー」ってよく聞く話ですが
110万円超えているからと税務署の調査を受けた話って聞いたことないです。
税務署(国税?財務省?)の周知不足なのか?
そもそも車購入時に他人からの支払いを受け付けるのがいけない?
住宅ローンと不動産の名義異なると指摘されるはずだから同じようにする?
銀行口座とマイナンバーで紐づけ出来たら解決できる問題なのか?
なんだかよく分からなくなってきましたが
課税の対象で申告納税漏れが悪いのではなく、期限後でも申告納税をすればOK
そして税務署の周知不足が悪いだけだと思います。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL